古代の皇帝は宮廷でどれほどの権力を持っていたのでしょうか?あなたはすべての最終決定権を持っていますか?
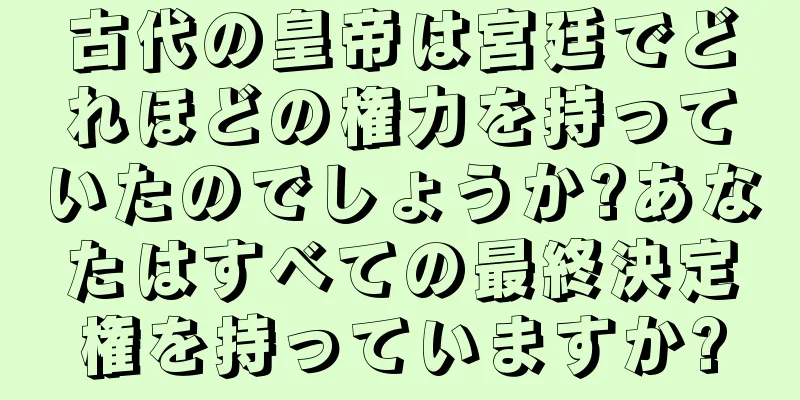
|
時代劇や映画を見ていると、古代の皇帝の言葉は金言だと感じることがよくあります。皇帝は、突然ひらめいたり、何かをしたいと思ったりすると、「勅書を起草せよ!」と叫んで、勅書を口述しました。勅令が書かれると、それはただちに最高法規となり、これに異議を唱える者は「勅令不服従」という重罪に問われることとなった。皇帝は強大な権力を持ち、何でも好きなことができるようです! もしこれが真実だと信じているなら、あなたはこのメロドラマ的なテレビシリーズによってどん底に導かれていることになります。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! では古代の皇帝はどれほどの権力を持っていたのでしょうか? まずは勅令から見ていきましょう! 勅令と三省制度 隋は二つの大きな改革を行なった。一つは秦漢時代の三官九大臣の官制を三州六省に改め、もう一つは科挙(今の大学入試に相当)を実施して人材を募ることだ!この二つの大改革は中国の歴史に数千年にわたって影響を与えてきた!その中でも三州は権力の中核であり、すなわち書記局、商書、孟下省である!機能分担は、書記局が勅令の起草を担当し、孟下省が勅令の内容の審査を担当し、不合理なところがあれば拒否する権利を持つ!審査で問題がないものについては、執行のために商書局に引き渡される! 唐と宋の時代を例に挙げてみましょう。勅令を発布する通常の手順は次の通りでした。まず首相府が案を書き、次に大臣たちが午前中に会議を開いて議論し、全員一致で承認を得て、その後、勅令の草案が皇帝に提出され、承認を得るというものでした。そして、官房長官(武則天の時代には馮閣と改名)は、それぞれが自分の考えに基づいて勅旨(草案)を書き、官房長官に送りました。官房長官は、その中から最良と思われるものを選び、修正・磨きをかけて本物の勅旨(草案)とし、皇帝に送って印章をもらい(皇帝は意見が異なる場合は、勅旨の余白に赤ペンでコメントを書き込むこともできますが、理論上は勅旨を直接拒否する権限はありませんでした)、人事部(武則天が皇帝になったときに桓台と改名)に送って審査・印章してもらいました。最終的に、執行のために事務局(現在の国務院に相当)に引き渡されました。 天皇は勅令の起草を直接指示する権限も持っていたが、官房が何かを書き、天皇が承認の印を押すだけのケースが多かった。つまり、勅令の実質的な決定権は官房にあり、天皇の役割はそれに署名し、印を押すことだった。人事省が勅令に納得できないと感じた場合、たとえ天皇がすでに同意の印を押していたとしても、人事省はそれを直接拒否する権利を持っていた。以上の手続きを経て、官房、内務省、皇帝の印を受けた勅書のみが有効な勅書となり、そうでない場合は違法となる。 天皇が勅令の内容に同意しない場合、大臣たちは国と国民を第一に考え、早く押印するよう天皇にせがみ続け、罷免や世論、さらには命まで脅迫する。つまり、必ず署名しなければならないのだ! 一方、皇帝が勅令を発布したいが、大臣らが反対した場合、どうすればよいのだろうか。これは非常に興味深い。歴史上、三省を迂回して密かに勅令を発布した皇帝もいた。例えば、則天武后はかつて自分の印章のみを押印し、奉格鑾台を迂回して「偽の勅令」を発布し、大臣らから非難を浴びた。唐の皇帝中宗は側近を任命したかったが、宰相たちが同意しないのではないかと恐れた。官房の二つの関門を越えられないだろうと、官房を迂回して「偽の勅令」を発布し始めた。しかし、やはり臆病だったため、署名には墨ペンを使用し(規定では赤ペンが必要)、勅令の捺印には斜印を使用し、官房が柔軟に執行すべきであることを暗示した。意外にも、突破不可能な壁はなく、このことは後に他の人にも知られることとなった。人々は中宗が個人的に任命した側近を「斜印官吏」と呼び、任命された側近たちでさえ恥ずかしがった。 宋代の皇帝は、中書社人による勅令の起草や介石中による審査といった法的手続きを経ずに勅令を発布することができ、宰相の連署も必要とせず、直接勅令を発布することができた。これを「直筆勅令」「内勅」「内批」などと呼んだ。今日の言葉で言えば、それは指導者が覚書を承認することを意味しますが、これは歴史上珍しいことではありません。しかし、このような私令には正当性がなく、「奉格鑾台から発せられなければ勅令とは呼べない」ということわざがあるように、政府が執行を拒否することもできる。つまり、三省機関の審査を受けていない勅令は単なる紙くずであり、役に立たないということだ。宋代の仁宗皇帝の時代、宰相の杜延は皇帝が個人的に発布した「直筆の勅書」を一切公開せず、十数部を集めてそのまま皇帝に返した。皇帝は何もできず、「大いに助けてくれた」と称賛することしかできなかった。一度そのような勅令が出れば、それは必ず永遠の不名誉をもたらすことになるだろう。 結論:ここから、古代では、天皇は好き勝手なことはできず、勅令も軽々に発せられることはなかったことがわかります。天皇の権力を牽制するこれらの機関(別の見方をすれば、天皇を補佐する機関でもありました)があったからこそ、天皇は勤勉に働き、少しも怠慢になることができませんでした。万暦帝が30年近くも国政を無視していたにもかかわらず、国が秩序正しく統治されていたのは、まさにこのような完全で成熟した権力機構があったからこそです。皇帝の権力が統制された制度のもとで、文官の地位は徐々に向上していきました。 宋代には文官の地位が最高潮に達しました。そのため、唐の太宗皇帝は魏徴を見て恐怖し、宋の仁宗皇帝は怒りのあまり泣きながらも大臣たちを褒め、鮑正は皇帝と口論して皇帝の顔に唾を吐きました!皇帝の権力が集中していた明代でも、文官は皇帝と対峙することによってのみ権力を恐れない誠実さを示すことができました!一方、対峙されることに耐えられる皇帝は怒らず、不快で正直なアドバイスにも耳を傾け、心が広い良い皇帝であることを証明しています! |
<<: 近代的な娯楽施設がなかった古代において、なぜ人々は夜更かしすることが多かったのでしょうか。
>>: 古代の地形は本当に存在したのでしょうか、それとも古代人によって発明されたものなのでしょうか?
推薦する
袁載舒はどのように発展したのでしょうか?袁紹城の発展史の詳細な説明
袁紹がどのように発展したかを知りたいですか? 袁紹は、大体金朝末期から元朝初期にかけて初めて登場し、...
西部記録第21章:軟水の海が硬水に取って代わり、磁力の尾根が天の兵士を借りる
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
イ族の文化 イ族の織物文化 「腰織り機」の歴史
中国では織物の文化が非常に長い歴史を持ち、最も古い織機は地面に座って織る織機で、一般に「腰織機」と呼...
北宋時代の不吉な政治環境の中で、なぜ厳叔は明らかに異端者だったのでしょうか?
顔叔とは誰ですか?なぜ宋の真宗皇帝は彼を高く評価したのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介...
日本の「切腹」とはどのようなものですか?なぜ日本でこのような死に方が人気があるのでしょうか?
日本の切腹について本当に理解していますか?Interesting Historyの編集者が、関連コン...
周の景帝が楊堅に譲位することを選んだのはなぜですか?彼の最終的な結末はどうだったのでしょうか?
周の宣帝が病死した後、後継者の周の景帝は幼く、義父の楊堅が摂政となり朝廷の権力を握った。その後、于池...
【新唐書・李凡伝】原文・訳:李凡、敬称:舒漢
李凡は、名を舒漢といい、趙州の出身であった。若い頃のファンは容姿端麗で、のんびりとしていて、勉強熱心...
荘子はどの学派に属していますか? 荘子の政治的見解は何ですか?
荘子は道教に属しており、道教は非常に強力な学派であり、さまざまな学派の中でも非常に賢明であると考えら...
七剣士と十三英雄第150章:呉天雄とその家族が戻り、玄真子が祭壇に登り命令を下す
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
黄景仁の『美思十六詩集 第15』:この詩は漠然とした悲しみに包まれている
黄景仁(1749-1783)は清代の詩人であった。号は漢容、別名は鍾沢、号は呂非子。楊湖(現在の江蘇...
蘇軾の「江南を観て、潮然台で書いた」:大胆さと優雅さを兼ね備えた詩
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
曹雪芹の詩「桃花歌」鑑賞
【オリジナル】桃の花桃の花のカーテンの外では東風が穏やかで、桃の花のカーテンの内側では朝の化粧が怠惰...
古代の銅貨はどんな匂いがしたのでしょうか?なぜ「石炭の匂い」という言葉が金持ちを揶揄するのに使われるのでしょうか?
古代の銅貨はどんな匂いがしたのでしょうか? なぜ「銅の匂い」という言葉が裕福な人々をあざけるために使...
『紅楼夢』で賈雲と出会う前と出会った後で、王希峰の態度はどれくらい変わりましたか?
『紅楼夢』は中国の四大古典小説の最初の作品であり、その登場人物は私たちに深い印象を残しました。 In...
武術だけを考えれば、なぜ張飛は関羽よりわずかに優れているのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...









