西漢時代に内外王朝制度が出現した理由は何ですか?その具体的な構成要素と構造は何ですか?
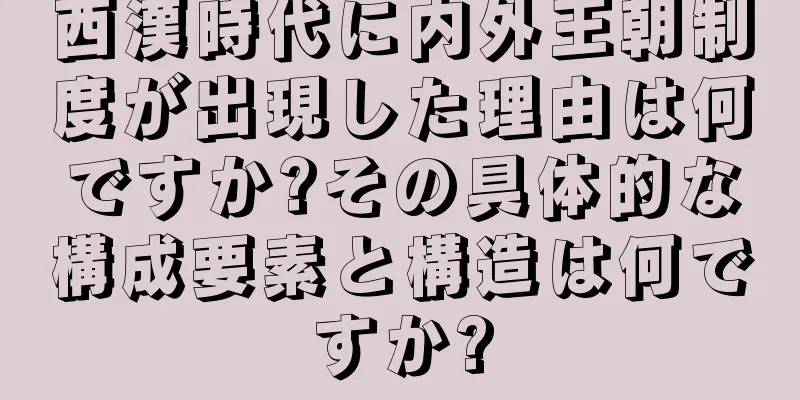
|
中外潮制度が生まれた理由は何でしょうか?中外潮の官僚の構成構造はどのようなものでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 中国と外国の王朝制度の簡単な紹介 中朝は皇帝の側近や賓客で構成される内廷です。外庭は公爵、大臣、役人を指して外庭とも呼ばれます。内廷と外廷の区別は武帝の治世中に現れた。前漢初期には皇帝が国政を司り、宰相も討議に参加した。 武帝は権力の集中化を強化するために宰相の権力を弱めた。重要な政治問題は、信頼できる腹心を頼りに宮廷内で決定され、こうして中朝関係が形成された。中央王朝があれば、当然、それとは異なる外王朝が存在することになります。外朝とは、宰相、検閲官、九人の大臣から構成される官僚制度を指します。 中国と外国の王朝制度が生まれた理由 前漢初期の政治体制では、宰相が大きな権力を持ち、皇帝は多くの事柄について宰相の意見を聞かなければなりませんでした。漢代には、宰相が中央の首都と郡の官吏を400段以下の官吏に任命する権利を持ち、また宰相は600~2,000段の官吏を推薦する大きな権限を持っていたと規定されていた。 武帝が即位すると、宰相の田分は皇帝の権威を無視し、民衆に二千石官位への昇格を推奨し、権力を皇帝に移譲した。宰相の権力が強大であったため、独裁権力を強化したい皇帝は宰相と衝突せざるを得なかった。漢の武帝は皇帝の権力を強化するために、首相の権力を弱めるために、意図的に側近たちに重要な問題の意思決定に参加させました。 皇帝に寵愛されたこれらの側近たちは、首相が率いる中央政府の外朝に相当する、いわゆる内朝を形成した。中国と朝鮮の官僚は皇帝の命令に直接従い、実権を握り、首相が率いる中央政府から意思決定機能を奪った。 外朝の組織構造は秦代や前漢初期のものと基本的に変わっていないが、機能面では一般的な政務の処理と執行のみを担当し、政府の命令を執行する機関となった。漢の武帝の治世中に内外の王朝が形成されたことは、中国の封建社会の政治体制に大きな変化をもたらした。 これは皇帝の権力と首相の権力の矛盾を反映しており、またこの矛盾を解決するための必然的な方向も示しています。つまり、皇帝の専制権力を強化するために、皇帝は側近を使って大臣の権力を奪い続けます。新しい機関がますます強力になり、皇帝を驚かせるほどの力を持つようになると、皇帝は信頼できる新しい大臣を使って別の機関を形成します。これが三省の形成過程であり、明・清朝における内閣と太政官の出現でもあった。 中国と外国の王朝の構成構造 中国と北朝鮮 一般的な 将軍は総大将、騎兵大将、近衛大将、前衛大将、後衛大将、左衛門大将に分かれます。漢王朝では、軍事権は皇帝が個人的に握っており、すべての将軍は皇帝によって任命され、指揮されていました。 将軍は皇帝と非常に親しい関係にあったため、秘密の協議にも参加していた。皇帝はまた、信頼する大臣たちに名誉を示すために将軍の称号を与えた。例えば、蕭王之は元々文官であったが、政務を補佐せよという勅命により将軍に任命された。 大臣たちを近づける 世忠、左草、幽草、諸官、三卿、長氏、介世忠などを含む。皇帝は、信頼する九卿やその他の官吏、儒学者に、本来の役職に加えて、士中、昌師などの称号を与えました。当時の人々は、これらの称号を「加称」と呼んでいました。 いわゆる「加官称号」は特定の職務を持たない称号だが、この称号を取得した者は故宮に出入りしたり、秘密の協議に参加したりすることができる。時には皇帝の意向に従って外廷の大臣を批判することもできた。前漢時代の側近たちは、実は皇帝の客人であり、スタッフでもありました。 シャンシュウ 尚書はもともと皇帝の傍らで文書作成を担当する下級官吏であった。中国と北朝鮮の台頭により、その地位は次第に重要になっていった。単に議論に参加する役人とは異なり、商書には官職、部下、特定の職務がありました。皇帝の官庁となり、次第に中国と北朝鮮で中核的な地位を占めるようになった。 昭帝の時代には、霍光が政務を執り、同時に書記官も務めた。その後、歴代の摂政大臣もこの例に倣い、書記官を務めた。 外庭 内閣総理大臣を長とする行政機関が「外朝」である。外朝の事務所は宮殿の外にあり、官職制度に属していた。ここから正式な勅令が発布された。 |
<<: 科挙の内容は何ですか?古代の科挙の採点はどのようなものでしたか?
>>: 北魏の三将制の背景は何ですか?三将制の歴史的意義は何ですか?
推薦する
ユンジンの価値は何ですか? Yunjin は開発プロセス中にどのようなカテゴリに分けられますか?
発展の過程で、雲錦は多くの品種を形成してきました。現在入手可能な情報から判断すると、大まかに「荘花」...
劉克荘の『武塵の年に関すること』:読んでいて面白くて面白いが、とても悲しい。
劉克荘(1187年9月3日 - 1269年3月3日)は、原名は卓、字は千福、号は后村で、福建省莆田県...
秦の歴史において、どの4大軍団が大きな役割を果たしましたか?
2000年以上前、秦の軍隊は六つの国を席巻し、世界を統一し、当時世界最大の帝国を築き、中国の歴史の発...
伏羲神話の紹介:伏羲三帝が龍を征服する物語
伏羲:伏羲(生没年不詳)、姓は馮、別名は米溪、宝溪、包溪、伏羲、西皇、黄溪、太豪で、『史記』では伏羲...
清朝における鄭皇旗の主な機能は何でしたか?苗字は何ですか?
まだ分からないこと:清朝の鄭隋旗の主な機能は何でしたか?どんな姓がありましたか?鄭隋旗は明朝の万...
「川は青い絹の帯のよう、山は翡翠の簪のよう」という有名な一節の何がそんなに美しいのでしょうか?
「河は青い絹の帯のよう、山は玉の簪のよう」という有名な一節の美しさは何でしょうか?この一節は『韓愈が...
宋代の詩を鑑賞する:風楽亭の春の外出、第3部:作者は詩の中でどのような比喩を使用しているか?
風楽亭春巡りパート3、宋代の欧陽秀、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介を持ってきますので、見てみまし...
劉備が四川に入る前に襄樊を攻撃しなかった主な二つの理由は何ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
後漢書 第三巻 粛宗孝章紀 原文
粛宗孝章帝の本名は殷であり、献宗帝の5番目の息子であった。母:賈妃。永平三年に皇太子に立てられた。彼...
顧凱之のサトウキビ食理論とは?顧凱之の洛神画を鑑賞
顧凱之は東晋の時代に生きた人物で、優れた才能の持ち主でした。詩や随筆を書くだけでなく、字もとても美し...
『紅楼夢』で賈舍が中秋節に語ったジョークはどういう意味ですか?
賈おばあさんは、石夫人とも呼ばれ、賈家の誰もが敬意を込めて「老夫人」「老祖」と呼んでいます。『興味深...
『詩経・国風・中南』の意味は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
中南匿名(秦以前)中南には何がありますか?川と梅の花があります。錦の衣装とキツネの毛皮を身に着けた紳...
『紅楼夢』の宝玉の処方箋は本当に林黛玉の病気を治せるのでしょうか?その背後にある比喩は何でしょうか?
『紅楼夢』の第三話では、林黛玉が賈一家に初めて会う。初めて会ったとき、誰もが彼女の内気な顔と艶めかし...
古典文学作品「東遊記」第15章:鍾離は谷に逃げた
『東遊記』は、『山東八仙伝』や『山東八仙伝』としても知られ、全2巻、全56章から構成されています。作...
『紅楼夢』で霊官は結局どこへ行ったのでしょうか?なぜ消えてしまったのでしょうか?
霊官は賈家の12人の小役者の一人です。容姿も性格も黛玉に最も似ています。興味のある方のために、「おも...









