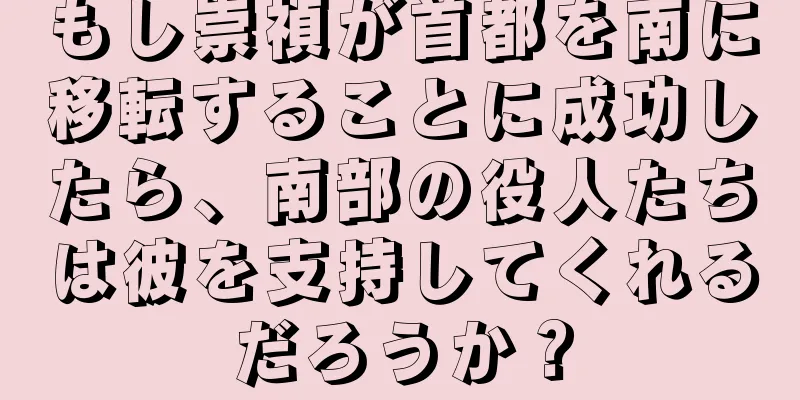本草綱目第8巻牡丹編の具体的な内容は何ですか?

|
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の Interesting History 編集者は、皆さんと共有するために関連コンテンツを用意しました。 この本は「要綱に従って列挙する」という文体を採用しているため、「綱目」と名付けられました。 『正蕾本草』に基づいて改正された。この本には190万語以上が収録されており、1,892種類の医薬品が収録され、11,096の処方箋が収録され、1,160枚の精巧なイラストが掲載されています。16のパートと60のカテゴリに分かれています。本書は、著者が数十年にわたる実践と研究を重ね、これまでの生薬学の成果を継承・総括し、長期にわたる研究と聞き取り調査を通じて蓄積した広範な薬学知識を結集してまとめた傑作です。この本は、過去の生薬学におけるいくつかの誤りを訂正するだけでなく、大量の科学的データを統合し、より科学的な薬物分類方法を提案し、先進的な生物進化の考えを取り入れ、豊富な臨床実践を反映しています。この本は世界的な影響力を持つ自然史の本でもあります。 本草綱目·第 8 巻·生薬·牡丹 【名前】 江里、麗石、百珠、玉容とも呼ばれる。白いものは金牡丹、赤いものは木牡丹と呼ばれます。 【コレクション】 【時珍曰く】昔の人は洛陽牡丹と揚州牡丹が世界一だと言っていた。現在医療に使われている薬品のほとんどは揚州産です。 10月に芽を出し、春に成長し始め、3月に開花します。千葉、一葉、塔葉など30種類以上の品種があります。薬用として最も適した根は、豊かで強い香りを持つ単葉の根です。根の赤と白は花の色に従います。 根(匂い)は苦くて、平らで、無毒です。 【五行説】牡丹の根は冷たく、酸っぱく、香りが濃く、味は薄く、上昇し、わずかに下降し、陽中の陰に属します。 【好古朮】 味は酸味と苦味があり、香りは薄く、味は濃厚で、陰に属し、主に下降に用いられ、手足の太陰経絡の月経循環の薬であり、肝、脾、血に入ります。 【智才曰く】徐巴とは相性が良く、石虎、芒硝とは相性が悪く、硝石、亀甲、小薊とは相性が悪く、紅参とは相反する。 【効能・効果】 邪気による腹痛を和らげ、瘀血を取り除き、固い塊を分解し、寒熱によるヘルニアを治療し、痛みを和らげ、排尿を促進し、気力を活性化します。血管の詰まりを取り除き、胃痛を和らげ、悪い血を分散させ、邪気を払い、水蒸気を取り除き、膀胱と大腸と小腸に利益をもたらし、化膿と腫れを取り除き、季節の悪寒と熱を和らげ、胃痛によって引き起こされる腹痛と腰痛を和らげます。内臓の気の蓄積を治療し、五臓六腑を強化し、腎気を補充し、季節性疾患による骨熱を治療します。女性の血液が詰まって自由に流れなくなると、膿が出ることがあります。女性のさまざまな病気、産前産後の病気を治し、風邪を治して疲労を回復し、熱を下げ、落ち着きのなさを解消して気力を活性化し、ショックと頭痛を治療し、目の充血と視力の改善、腸の風、出血、痔、瘻孔、腰痛、疥癬に効果があります。肝臓を浄化し、脾臓と肺を落ち着かせ、胃の気を吸収し、下痢を止め、毛穴を強化し、血管を調和させ、陰の気を吸収し、逆の気を抑制する効果があります。中気を調整し、脾虚、中膨満、心膨満、肋骨痛、げっぷ、肺の急性膨満、喘鳴・咳、太陽経絡による鼻血・ドライアイ、肝血虚、インポテンツ、悪寒・発熱、帯経絡病、腹痛・膨満感、水に座ったような腰痛などを治療します。下痢を止め、腹痛や重苦しさを和らげます。 【発明】 【大明曰く】赤は気を補い、白は血を補う。 【五行説】白は滋養し、赤は散じて肝臓を清め、脾臓と胃を滋養する。月経中にワインを飲むと、中腹部の痛みが止まります。生姜と一緒に使用すると、経絡を温め、湿気を取り除き、閉塞を解消し、腹痛や胃の停滞を緩和します。白芍薬の根は脾経に入り中焦を養うので、下痢には欠かせない薬です。下痢と軟便はどちらも太陰病なので見逃してはいけません。腹痛には煎った甘草の根を補い、夏には少量の黄耆を加え、寒さに弱い場合はシナモンを加える。これが張中景の魔法の処方である。脾経を鎮める、腹痛を治療する、胃気を調整する、下痢を止める、血液循環を調整する、皮膚を強化するという6つの機能があります。 【時珍曰く】白芍薬の根は脾臓に効き、土から木を浄化する働きがある。背中は重く、邪気を払い、血液の滞りを解消します。 根 【主な効能】五臓六腑を強化し、腎気を補い、季節病や骨熱を治療する。女性のさまざまな病気、妊娠前後の病気を治療し、風邪を治して疲労を回復し、熱を下げ、落ち着きのなさを和らげ、気を活性化し、ショックと頭痛を治療し、目の充血と視力の改善などに効果があります。 【追加処方】 1. 腹痛。白芍薬の根3グラムと焙煎した甘草1グラムをボウル2杯の水に加え、1杯の水で沸騰させて温かい状態で飲みます。夏に悪寒がある場合、オウゴン5分と桂皮1銭を加え、冬にひどい風邪がある場合、桂皮をもう1銭加えます。 2. 風毒による骨の痛み。牡丹2分と虎骨1両を煎って粉末にし、布袋に入れて3リットルの酒に5日間浸します。 1日3回、1回につき3杯のアルコールを飲みます。 3. 腫れて痛い水虫。芍薬六両と甘草一両をすり潰して粉末にし、熱湯とともに服用します。 4. 喉の渇きを癒し、水分補給を促します。白芍薬の根と甘草を同量ずつ使い、粉末状にします。毎回コイン1枚を取り、水で煎じます。 1日3回服用してください。特殊効果付き。 5. 鼻血が止まりません。牡丹を粉末状にすりつぶし、スプーン2杯ずつ水と一緒に摂取します。 6. 鼻血と喀血。白牡丹1両と犀角粉2銭半をすりつぶして細かい粉末にし、小さじ1杯を水で飲みます。出血が止まるまで。 7. 不正出血および下腹部の痛み。牡丹1両を黄色くなるまで炒め、ヒノキの葉6両を軽く炒めます。毎回2両を取り、水1リットルを加えて6合に煮ます。別のレシピ: 上記の 2 つのハーブを粉末状にします。 1回につき2銭をワインと一緒に摂取してください。 8. 月経が止まらない。白芍薬、芍薬、ヨモギをそれぞれ1銭半ずつ水で煎じて経口投与します。 9. 白帯下が長期間治らない。白芍薬の根3両と乾燥生姜半両をすり潰して粉末にします。空腹時に、1回につきスプーン2杯を水と一緒に摂取してください。 1日2回提供されます。別のレシピ:牡丹を黒くなるまで炒め、粉末にしてワインと一緒に飲みます。 10. 魚の骨が喉に刺さった。白芍薬の根を噛んで汁を飲みます。 |
推薦する
岑申の古詩「私が初めて官吏に任命されたとき、高官の草庵に刻まれた」の本来の意味を理解する
古詩「私が初めて官吏に任命されたとき、高官の茅葺き小屋に刻まれたもの」時代: 唐代著者: セン・シェ...
トゥチャ族の習慣と習性 トゥチャ族の葬式舞踊の起源
葬送舞は葬送太鼓舞とも呼ばれ、トゥチャ語で「サルヘ」と呼ばれています。恩施のトゥチャ族の古代の葬送儀...
「北清班」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
悲しい青坂杜甫(唐代)我が軍は東の門である青板に駐屯しており、寒いときには太白洞で馬に水を与えている...
ガルーダ:古代インド神話の巨大な鳥。仏教の八大神のうちの1柱。
ガルーダは、古代インドの神話に記録されている巨大な神鳥です。ヒンズー教では、三大神の一人であるヴィシ...
曹操の「志の文」の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
曹操の『叔子霊』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?これは多くの読者が知りたい質問です。次の興...
宋王朝が最終的に滅亡した根本的な理由は何だったのでしょうか?一杯のワインを飲みながら軍事力を解放することと何か関係があるのでしょうか?
一杯の酒をめぐって軍事力を解放することは、宋の太祖が皇帝の権力を強化し、統治を強化するために行った一...
『清代名人逸話』第3巻の情況欄には何が記されているか?
◎若い頃の阜陽出身の董邦達阜陽出身の董邦達は若い頃、優秀な貢学生として都に留まり、武林会館に住んでい...
歴史上トップ10の貴族の家系は何ですか?古代の貴族上位10家の一覧
歴史上、トップ 10 の貴族一族はどこでしょうか。これらの一族は、中国の長い歴史を通じて常に高い地位...
司馬遷は歴史上どのように評価されていますか?趙毅はそれを「歴史家の究極の原則」と呼んだ。
司馬遷は歴史上どのように評価されているのでしょうか?以下の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、...
『紅楼夢』では、青文は賈夫人の支援を受けていたのに、なぜ西仁を倒せなかったのでしょうか?
『紅楼夢』では、青文は賈夫人の支援を受けていたのに、なぜ西仁を倒せなかったのか?実は、その答えは方観...
楊万里の『新市徐公店滞在記 上』は、子供たちが蝶を追いかける場面を細かく描写している。
楊万里は、字を廷秀、号を成斎といい、南宋時代の詩人、作家である。陸游、幽當、樊成大とともに「南宋四大...
ウー・ジンシャオは、外見は甘く見えても中身は苦い、栄果屋敷のイチジクの葉をどうやって発見するのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『張普社に答える辺境の歌 第一部』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
張普社作詞の歌「辺境の歌」の第一曲呂倫(唐代)金色の召使いの少女には鷲の羽があり、刺繍されたサソリの...
前漢時代の儒学者・光衡とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は光衡をどのように評価しているのでしょうか?
匡衡は、字を智桂といい、後漢末期の人物である。生没年は不明である。前漢の儒学者で、宰相を務めた。「壁...
なぜ高秋は林冲を陥れたのか?高秋が林冲を陥れた経緯
なぜ高秋は林冲を陥れたのか? 高秋はどのようにして林冲を陥れたのか? (?-1126)は、北宋末期の...