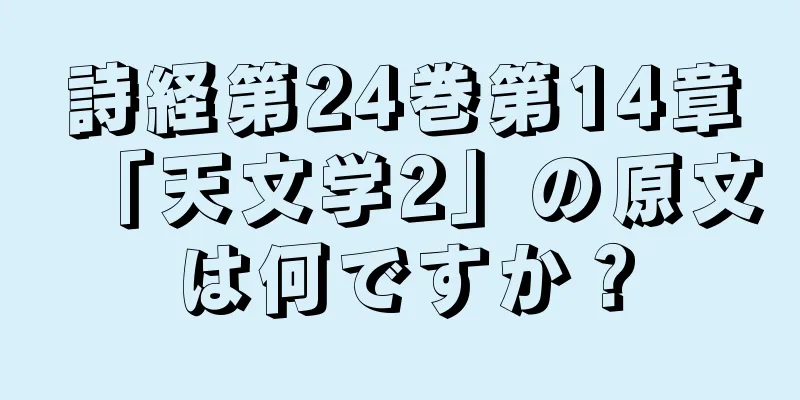明代の皇帝、献宗の三つの悪政は、後の明代にどのような影響を与えたのでしょうか。

|
明朝の後の世代に深刻な影響を与えた悪政といえば、明朝の献宗皇帝の治世中に行われたものが最も多かったと言えるでしょう。さらに、これらの悪政策は、明王朝の後代に取り返しのつかない影響を与えたとされ、これらの悪政策の発生こそが、当時の明王朝の衰退を早めた原因であった。王朝全体の観点から見れば、それは当時の明王朝に直接的な影響を与え、当時の朝廷を混乱に陥れたとも言える。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 西方工場は明代の成化13年(1477年)に設立されました。当社は西城区霊吉宮前の灰工場に設立されました。西工所の設立後、王直は金義衛の権力を利用して全国にスパイ網を展開した。当時、西工場のスパイの総数は東工場の2倍でした。東邑の宦官である尚明も、王直に従わざるを得なかった。 その結果、西廠は非常に傲慢になり、設立当初は大規模な粛清まで行いました。この状況は、当時の尚陸大書記と項忠陸軍大臣に心底嫌われる原因となりました。尚魯は献宗皇帝に西倉の廃止を提案した。主な理由は、西倉が都の三位以上の官吏から財産を恣意的に没収していたためであった。しかし、同年6月、尚陸、向中らが相次いで解雇され、西工場は復活した。この修復は明代の成化18年(1482年)まで続いたが、王直が失脚したため取り消された。結局、西方工場は明代の成化年間に5年数か月間存在したことになる。 一方、明の成化年間の西工は、明のスパイの機能と調査範囲を拡大しました。調査場所は首都と地方に限定されず、全国の南北の国境にまたがっていました。これは、以前の東工にはなかったことです。一方、献宗皇帝による西工の設立は、皇帝の諜報機関への偏愛を間違いなく強化しました。その後、献宗皇帝の孫である武宗皇帝は祖父の例に倣い、西工場を再建しただけでなく、内工場も設立しました。諜報機関の存在により、本来は召使であった将官が遠慮なく大臣を辱めることが可能になった。これは明朝の革新と言えるだろう。 明代中期の皇室農場の設置から、明代後期の鉱山監督や税務監督官としての宦官の派遣に至るまで、その目的は、王族が宮殿での贅沢な日常生活を実現するための多額の資金を集めることにありました。 「黄荘」という名前は、皇帝の献宗朱建真に由来しています。天順8年(1464年)、朱建深は宦官曹継祥の順義の農地を奪い、「皇室農場」とした。しかし、御料田は天皇だけの領地ではなく、天皇本人、側室、皇太子、都の王たちの領地も含まれており、つまり天皇とその妻、そして子供たちの領地であった。したがって、皇帝が封地を与えられた後に北京を離れ、自分の領地に戻った場合、その領地で得た農地はもはや皇室の農場として数えられなくなる。 皇室農場の設立は、実際に明代における土地併合の先例となった。朱建神の皇室農場は急速に順義、宝地、豊潤、新城、雄県などの地域に広がった。皇帝は土地資源の併合を主導し、王子、貴族、宦官も皇帝に土地資源の付与を求めたため、王領の田畑や官圃が存在した。明代の嘉靖年間初期に、表面上は皇室農場が廃止され、官墾地と改名されたが、それは単に名称が変更されただけで、実質は同じままであった。したがって、献宗が皇室農場を設立した行為は、間違いなく民衆と富を競い合い、王朝の経済に損害を与えていた。 天順8年(1468年)2月、即位してまだ1ヶ月も経っていない朱建深は、姚王という名の侍従を文氏遠の副使に任命する勅令を出した。これが「川風観」の始まりでした。 「川奉官」とは、当時、人事部、選抜、皇帝の推薦、大臣の協議を経ずに皇帝が直接任命した高官を指す言葉であった。明らかに、これはすべての通常の手順に違反していましたが、皇帝や後宮の側室や宦官の願いを叶えるためだけのものでした。 それ以来、皇帝は官職の称号を自分の私有財産とみなすようになった。皇帝は望む限り、高官を意のままに任命することができ、それによって皇帝と官僚や文人との間のバランスが破壊される。官吏は皇帝によって直接任命されたため、そのほとんどは通常の手段では官職を得ることができませんでした。文民政府にとって、軍人出身の高官、僧侶、職人、画家、医師などが多数を占めることは、必然的に政府のアイデンティティに問題を引き起こし、政府部門の運営における矛盾を悪化させる。官吏は皇帝の勅令によって直ちに任命され、人事省による審査を受ける必要がなかったため、宮中で実権を握っていた側室や宦官は皇帝の名を利用して私利私欲を追求し、官職や称号を売り渡すことができた。 |
<<: 唐代の詩人、杜甫といえば、なぜ彼は生涯貧しかったのでしょうか?
>>: 劉邦は単なる村長に過ぎなかったのに、なぜ自分より権力のある人々を支配できたのでしょうか?
推薦する
水滸伝で宋江は涼山に行った後、趙蓋にどのように挑戦しましたか?
宋江が涼山に赴いた後、単に酒を飲み肉を食し、金銀を分けることはもはや彼の追求ではなくなった。彼は「黄...
女真文字はどのようにして誕生し、発展してきたのでしょうか?女真文字を作成した目的は何ですか?
女真文字は、中国の古代少数民族である女真族が、女真語を記録するために使用しました。女真文字は、金王朝...
『紅楼夢』の怡宏院で舒月はどうやって身を守ったのでしょうか?
麝香月は、易虹院の四人のメイドの一人であり、『紅楼夢』の登場人物である。 Interesting H...
水滸伝で趙蓋はなぜ失敗したのか?原因は何ですか?
小説『水滸伝』の登場人物で、「刀太天王」の異名でも知られる趙蓋は、涼山坡の領主である。以下の記事はI...
「夜、ルーメンに帰る歌」は、孟浩然がルーメンに隠遁していたときに書いたもので、隠遁生活の気持ちを表現している。
孟浩然は、本名を孟浩といい、浩然、孟山人とも呼ばれ、唐代の山水田詩派の代表的人物で、王維とともに「王...
宋代の詩「醜奴」の鑑賞 - 「私は夜に酔いから目覚め、夢を見ない」。この詩は何を描写していますか?
醜い奴隷·酒に酔って夜は目が覚めて夢を見ない[宋代]秦管、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介を持って...
Sajia とはどういう意味ですか?歴史上のサジアの名前の由来
『慈海』改訂版には、「撒」(発音はsǎ)は「宋元時代の関西方言の『撒家』の略語で、『赞』と同じ」とあ...
「春の夜に嬉しい雨」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
春の夜の雨杜甫(唐代)良い雨は季節を知り、春に降ります。風とともに夜に忍び込み、音もなくすべてを潤し...
『農桑家要』:蚕業の準備:「蟻」の全文と翻訳ノート
『農桑集要』は、中国の元代初期に農部が編纂した総合的な農業書である。この本は、智遠10年(1273年...
文公13年の儒教古典『春秋古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
袁紹には多くの顧問がいたのに、なぜ正しい選択肢をすべて避けたのでしょうか?
官渡の戦いは、数で劣る側が勝利した戦争の歴史上有名な例です。曹操はわずか7万人の兵士で袁紹の70万人...
羌族の刺繍を披露:羌族の美しい風景
「この光景は言葉では言い表せない。羌族の少女が正面で刺繍をしている。」羌族の村でこのような言葉を聞く...
明代の衣服:明代の如群
明代の服装スタイルは上着とスカートで、唐代や宋代のものとあまり変わりませんが、若い女性は動きやすさを...
諸葛亮はなぜ晩年はいつも戦いに負けたのでしょうか?諸葛亮は本当に年老いていて精神的に欠陥があるのでしょうか?
『三国志演義』を読めば誰もが理解できることの一つは、劉備の死後、蜀が戦いに勝つことはほとんどなかった...
「中国の工房からの奇妙な物語」の「針縫いの章」はどんな物語を語っていますか?原文はどのように説明されていますか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「縫い針」の原文于小思は東昌出身である[1]。生活し、富を蓄...